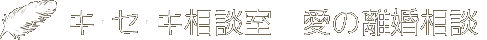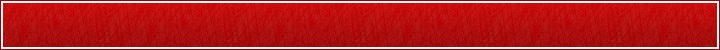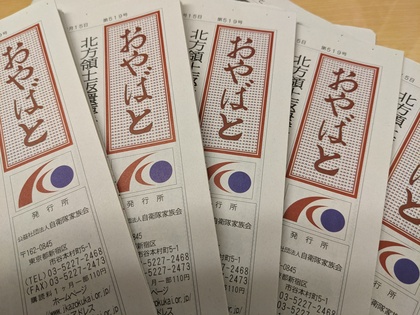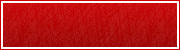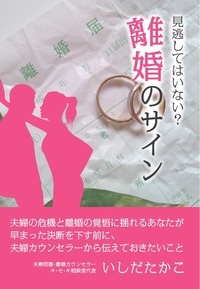子供をめぐって 〜親権と監護権〜
未成年の子供がいる夫婦が離婚をする際、どちらが引き取って養育をするかを決めなければなりません。夫婦間の協議(話し合い)で決まらない場合は、家庭裁判所での調停や裁判で決めることになります。
この子供を養育する親に与えられた身分上・財産上の権利や義務を総称して「親権・しんけん」といいます。
親権には大きく分けて二つの柱があります。
①親として未成年の子と共に暮らし、生活上の面倒を見ること
②未成年の子の法定代理人として、財産管理や法律行為を行うこと
そして場合により、①を「監護権・かんごけん」、②を「親権」と称して、分けて考えることもあります。
子育てという観点から、離婚後は主に母親が親権者となるケースが多いのですが、もちろん父親でもなれます。その子供にとって父と母、どちらで養育された方が望ましいのかが判断基準になります。
本来子供を引き取る方の親が、養育する監護権と法定代理人の親権を併せ持つ方が都合が良いのでしょうが、子供の取り合いで離婚話が進展しなくなってしまうこともあります。
そんなときは夫婦で監護権と親権を分けて持つ方法があります。
離婚後に子供を母親が引き取るのであれば、母親が監護権を持ち、父親が法定相続人としての親権を持つことができます。一緒に暮らさない父親も、親権者として子供の成長に直接関わる事ができます。
離婚後に母親(モト妻)から子供との面会を拒否されそうな心配(※)がある父親には、面会確保の保険代わりにもなるでしょう。また母親からしたら、モト夫からの養育費が滞る不安(※※)が軽減するかもしれません。子供の成長のために、離婚後も必要に応じて互いに連絡を取り合っていくことになります。
なお、監護権や親権を持たないからといって親子関係が消滅するわけではありません。扶養の義務や相続の権利などはちゃんと残ります。
親権を争うのは子供が未成年の間のことです。ある程度の年齢に達すれば、子供は自分の意思で親の間を行き来するでしょうし、成人すれば自分の意志で生活もしていけます。
子供が大きくなったときに、親として認めてもらえるような生き方を示すことも大切ではないでしょうか。
子供の取り合いも子供にとってはつらいことですが、くれぐれも子供の押し付け合いだけはしないで下さいね。子供は親を選べませんから。
※親権の有無や養育費の支払いを理由に、離れて暮らす方の親と子供の面会を拒否することはできません。
※※養育費の支払いは離婚理由に関係なく、子供に対する親の義務なので放棄できません。しかし現実には途中で養育費が払われなくなることは珍しくありません。