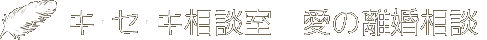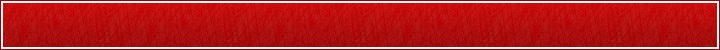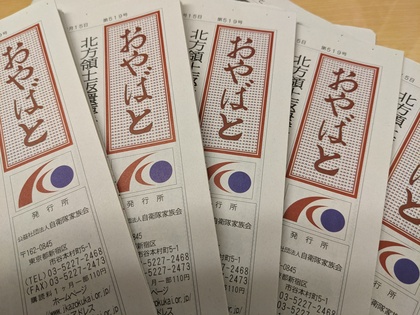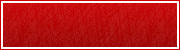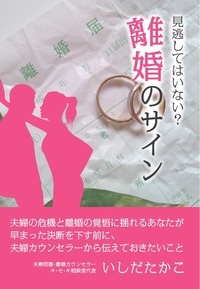モラハラとサラミ戦術
「サラミ戦術」という言葉をご存じでしょうか。
外交などの交渉の場で、少しずつ相手の譲歩を引き出しながら自分に有利につなげていく方略です。
サラミソーセージをごく薄く削いで食べていき、最後には完食する様子に似ていることから名づけられた戦術です。
夫婦間のモラハラの背景にもこのサラミ戦術が隠れている場合が往々にしてあります。
最初は小さな「おや?」から始まり「このくらいなら目をつぶっておこう」と考えます。
でも最初に「これくらいなら」と考えたので、次回同様のことが起きたときも前回同様「目をつぶって」しまいます。
心理学ではこれを一貫性の法則と言い、人は一貫した行動・発言・態度を取りたいという心理のことを指します。
しかしこれは「思考停止」を招きます。
やがて気が付けば事態はエスカレートしており、自分一人で対処することが困難な状況になります。
ちょっとここでフランスの作家フランク・パブロフの『茶色の朝』という短編小説を紹介したいと思います。
真綿で首を絞めるようにじわじわと異なる主義主張に世の中が変えられていく恐ろしさが、寓話で表現されています。
多くの人に読んでもらうために、作者は著作権を放棄したそうです。
ネットでも読めるので、ぜひご一読をお勧めします。
http://www.tunnel-company.com/data/matinbrun.pdf
※この小説は政治的な意味で解釈されることが多いですが、小説なので読み方は読者の自由です。
いしだは、思考停止に陥らないことの大切さを汲み取っています。
モラハラとサラミ戦術<下>に続く